石塚正英
まえおき
大類伸『史学概論』共立社、1941(初1932)年、からの【引用】と【注記】。文中の「/」は改行を示す。下線は引用者による。引用に際し、(中略)を挿入して必要箇所の抜粋にとどめている場合がある。文中の漢数字は算用数字に変えてある。注記に当たっては、引用者がこれまでに論文として蓄積してきた研究成果を利用している。大類伸(おおるい・のぶる、1884-1975)は、1924年から1944年まで東北帝国大学法文学部史学科で、主に中世文化史の研究と教育に勤しんだ。同僚にはフランス近代史の中村善太郎(1879-1932)が、高弟には史学史の酒井三郎(1901-82)がいる。ちなみに、酒井は私の恩師である。
☆ ☆
【引用01】歴史に於ては「発展」の概念がいかに重要な意義をもつかは云うまでもない。(中略)実に史的観念と発展観念とは不可分の関係にあるもので、後者なくして前者は成立し得ないのである。(5頁)
【注記01】「史的観念と発展観念」、この2語を合わせると、大類の主張は進歩史観の称揚ということになる。ただし、「発展」には量的な相違のほかに質的な相違があるのではないか。それを考量すると、歴史発展には類型の差異が存在するのである。大類が「史的観念」という場合、それは幾分とも類型を形成するはずである。例えば北欧的なモノクロニックと南欧的なポリクロニックというような類型である。
【引用02】彼(ヘーゲル:引用者)に於て歴史は始めて其の個別性に於て充分生かされながら、歴史全体としての大なる総合にまで、必然的に系統的に包括されることとなった。リッカートの如きは歴史認識の個別化的な論理を建てるに努力したことは偉大であるが、彼には歴史に最も重要なる「発展」が希薄である。(6頁)
【注記02】「発展」を重視する歴史観は19世紀の歴史主義の特徴である。歴史主義は、歴史を個性の発展とみなす立場であり、19世紀前半から現在に至るまで主流をなしているが、とくにドイツではこの傾向が強く、19世紀のドイツは「歴史主義の世紀」とまで称されている。その19世紀の歴史学を大別すると、①政治史的傾向(ランケが代表)、②経済史的傾向(マルクスが代表)、③文化史あるいは精神史的傾向(ブルクハルトが代表)の3方向に区別できる。けれども、20世紀に至って歴史を世界史として鳥瞰するならば、そこには「横倒しの世界史」が広がっている。北半球と南半球との区別なく、豊かな類型と貧しい類型がここかしこに並存し、国の内に一瞥を投げても、所得格差の歪みは陰に陽に発現している。そのような情勢を産み出してきた世界史的背景について、私は「横倒しの世界史」と形容している。2023年5月、広島市で先進7カ国首脳会議(G7サミット)が開催された。核軍縮に関する初の独立文書「広島ビジョン」を打ち出して閉幕したこの国際会議には、いわゆるグローバル・サウスと称される国々も参加した。セッション4「パートナーとの関与の強化(グローバル・サウス、G20)」がそれである。その際、主催者や報道陣は「グローバル・サウス」を「パートナー」と呼ぶほか、「新興国・途上国」とも表現していたが、その日本語は正しくない。その語は、かつて1960年代に激化した南北問題、南北経済格差に常用された同時代語だったが、2020年代の現在にはふさわしくない。南北問題・格差を英語では“North-South divide”と表記する。そこには豊かな北半球と貧しい南半球という意味合いが含まれていた。しかし昨今では、資源ナショナリズムなどを背景として南にも豊かな国々が登場し北にも貧しい国々が出現している。今回のG20にはインドを筆頭にグローバルに経済活動を拡大している南の諸国が参加している。経済力や技術力の面でもはや新興でもなければ発展途上でもなく、南も北もいわば横一列に、グローバルに並んでいるのである。私はこの国際情勢を指して「横倒しの世界(史)」と称することにしている。
【引用03】さて啓蒙時代が、歴史の解釈に対して如何なる功績を有するかを明らかにするには、モンテスキュー、ヴォルテール、ギボン等の人々を思い出せばよいであろう。しかし彼等は要するに合理主義的な経験を根底として立つものであって、科学的な歴史哲学については勿論語って居ない。又たとい世界史の精神的全体形相を問題にしたとしても、それは本来神学的な根拠の上に立つものに過ぎない。(11頁)
【注記03】とりあえず18世紀の啓蒙期の歴史観が問題となる。ルネサンスとこれに続く宗教改革とによってヨーロッパに人間主義が広まったが、その後17世紀から自然科学が発達しだすと、これを背景にして人間主義は合理主義的な傾向を強めていく。この傾向は、18世紀の啓蒙主義者がとり入れるところとなり、歴史についても一つの理論を形成した。例えばフランスの啓蒙主義者モンテスキューは、1734年に『ローマ盛衰の原因に関する考察』を、また1748年には有名な『法の精神』を著したが、それらの中で、人間理性に絶対の信頼をおき、理性こそこの世界を支配するもっとも根源的な法則であり、したがって歴史はこの普遍法則のあらわれであるという見解を表明した。また同じフランスの啓蒙主義者ヴォルテールは、1729年に『シャルル12世史』を、また1751年には『ルイ14世時代』を著し、文化史的叙述を残したが、彼の立場もまた「歴史の世界は哲学精神の進歩、哲学による開花、つまり理性が進歩し完成する過程である」と述べて、歴史を、人間に普遍的に備わる理性の進歩過程とみなした。だが大類は、それらを「本来神学的な根拠の上に立つものに過ぎない」としている。それでは歴史のダイナミズムが見えてこない。中世的唯一神思想がぐらついて、一方にはヴォルテールらの理神論が、他方にはスピノザをはじめとする汎神論が登場してくる。ついにはドルバックらの無神論が導かれてくる。啓蒙期の思想はその文脈に位置付ける必要がある。なお、啓蒙期の思想と啓蒙思想とは別物である。前者は必ずしも啓蒙思想にくくることのできないものである。ルソーなどはその一例である。参考:石塚正英「啓蒙期歴史学とルソーの叙述―歴史知的考察」、同『歴史知のアネクドータ』社会評論社、2022年、第6章。
【引用04】ヘーゲルは未来に対しては何等の変化をも予想して居ない。自己は原理的には既に終ってしまったことに属すると彼は考えた、従って彼は偉大なるものを過去の理解に求めこそすれ、未来の想像のうちに求めようとはしなかったのである。(Troeltsch 253-255)/しかし我等はなお茲に弁証法そのものに就いて考えて見なければならない。弁証法とは要するに過程の法則である。元来弁証法そのものの性質は、窮極を認めないものであり、永遠に発展する相を追うものなのである。然るにヘーゲルは過去のみに眼を向けて、未来には眼を向けなかった。かくして彼の弁証法は過去を理解する為にのみ用いられた。しかし弁証法の正しい適用は単に過去にのみ限られるであろうか。ヘーゲル自身は体系を求めねばならなかった。体系はある終極を要求している。従って体系そのものが、ヘーゲル体系の根底をなしている弁証法そのものを限定するに至ったのである。(20頁)
【注記04】大類が認める「体系そのものが、ヘーゲル体系の根底をなしている弁証法そのものを限定するに至った」という事態は、ヘーゲル学派の解体とヘーゲル左派の登場を促した。1835年、ヘーゲル学徒の一人ダーフィット・シュトラウスは、1835年と翌年、テュービンゲンにて『イエスの生涯』(全2巻)を刊行した。その中で師ヘーゲルの哲学体系(宗教哲学)に挑戦、学派分裂に火をつけた。ヘーゲルが1831年に歿して数年ののち、学派内には、師の哲学の解釈をめぐって論争が捲き起こった。その争点は、ヘーゲル存命のあいだには顕在化しなかったが、そもそもヘーゲル哲学中に潜んでいたものであった。ヘーゲルは常日頃、キリスト教に対し絶対的な価値を与えていた。またかれは、哲学と宗教の一致を主張していた。哲学は、宗教が想像力や形象によって捉えるものを、概念的に明白にするだけだというのである。これらが、学派内で論争の種となり始めた。師の主張をそのまま是認する一群は、それとともに、現在を完結したものと見做し、師の「現実的なものは理性的である」という命題を固執した。これに対し、師の主張に疑いを差しはさむ一群は、現在は完結を必要としているのだと判断し、師の「理性的なものは現実的である」という命題を強調したのである。この見解の相違は、前者を右派、後者を左派として、学派の分裂にまで発展する。その分裂は、1835年に出版されたシュトラウスの『イエスの生涯 Das Leben Jesu』が捲き起こした論争によって決定的となった。参考:石塚正英『ヘーゲル左派という時代思潮―A.ルーゲ/L.フォイエルバッハ/M.シュティルナー』社会評論社、2019年。
【引用05】そうして我々は信ずる、ヘーゲルが将来を問題としなかった点に於て、却ってヘーゲルの史家としての正しい態度が発揮されているのではないかと。弁証法を徹底的に活用することは、やがて歴史の個別的な形相を蹂躙する結果に終るのではないかと。(21頁)
【注記05】大類は、「将来を問題としなかった」ヘーゲルやランケに代表される19世紀の歴史主義に賛意を表している。ランケは、1818年、ライプツィヒ大学を卒業、1825年までフランクフルト・アム・オーデルの中学講師となる。その間、ニーブールの感化を受けて歴史研究に入り、1824年に「ローマ風・ゲルマン風諸民族の歴史」を発表して認められ、1825年以降ベルリン大学の教壇に立った。1828-1831年に、史料調査のためイタリアに旅行した。この成果は著作「ローマ法王史」(1834-37)となった。また、帰国後、一時、政府の依頼で、フランスよりの自由主義思潮に対抗する学術雑誌「歴史政治雑誌」を編集、しかし1836年再びベルリン大学に帰り教授となる。ランケによると、歴史家の任務は「ただ過去がいかにあるかを示すのみである」とされる。その態度は、私にすれば納得できない。私としては、むしろクローチェ(1866-1952)が唱えた「すべての歴史は現代史である」に共鳴する。なぜならば、過去からの連続としての現代史を問うことは未来へと連続する現代史を問うことになるからである。過去のある史実に関心をもつ理由は、現在のある事実や現象に関心をもつからである。現在を真剣に生きようとする者は過去を真剣に捉えようとする。そのとき、過去は過去的過去でなく、現代的過去なのである。あるいは過去・現在の時間軸を往復運動する生なのである。歴史とは、だれかある人、ある人々が物語るものであるとするなら、歴史の起点は過去にはない。あるいは、過去から現在へと単線的に発展する歴史などありはしない。歴史の前には、物語る人の実存がまずある。その一点においてクローチェの言葉「すべての歴史は現代史である」や、E.H.カー『歴史とは何か』(1892-1982)の言葉「歴史とは現在と過去の対話である」(清水幾多郎訳、岩波新書、1962年、40頁)は卓見であると言える。
【引用06】「自然に於ては新しきものなし」と云われている如く、自然に於ける変化は単に循環に過ぎないのに反し、精神に於て常に新しきものが生れ、より善きものより完全なるものへの衝動が認められる。自然に於ては変化はあっても発展はあり得ない。発展は精神に於てのみ認められる。自然における変化は矛盾や障害のない平穏な成長であるが、之に反して精神の発展は自己の内に於て自己と闘うことに外ならない。(28頁)
【注記06】1932年(本書刊行時)の大類は、歴史は「精神の発展」だとみる。それは一種のヘーゲル主義であり、進歩史観にたつものである。その史観の行き詰まりを経験した21世紀のこんにち、私は〔多様化史観〕を唱えている。19世紀の歴史家たちは、進歩史観でもってギリシア時代以来の循環史観を克服した。けれども、21世紀の歴史家たちは、こんどはその進歩史観をもう一つ別の史観によって乗りこえなければならない。この課題を、私は知の枠組みに関連させて、「歴史知(Historiosophy)」という用語で提起している。経験知や感性知など前近代に根をもつ知と、科学知や理性知など近代に成立した知と、その双方を時間軸上で――将来的に――連合させる試みである。自然と人間、感性と理性、野生と文明、前近代と近代、非合理と合理、ファシズムと民主主義といった二項対立をとらず、諸々の価値や概念を二項間の交互的往復運動の中に投げ込む。どちらかの項に意味や価値があるのでなく、二項間の〈交互運動〉にそれらを見いだす。そのような発想のもとに新たな歴史観を展望するならば、それは循環史観と進歩史観を連合させる史観、筆者の造語で表現するならば、「多様化史観(a diversification historical view)」となる。
【引用07】「現在の生の関心のみこそ、人を動かして過去の事実を知ろうとさせるのである」とはクローチェの言葉である。過去の事実は現在の生、現在の精神の要求によってのみ再び呼び起され、現在の関心と一致結合された時「過去の関心にではなく、現在の関心に答えるものである」と云い得るであろう。(47頁)
【注記07】クローチェの発想は単なる温故知新とは違う。ただし、「過去の事実は現在の生、現在の精神の要求によってのみ再び呼び起され」とある箇所は、1999年頃から私が唱えてきた「歴史知」の視座とは異なる。ところで、クローチェは、あるところで関係論的主権論を提出している。「およそいかなる国家にあっても人は誰でもその時と場合に応じて主君でもあれば臣下でもある(中略)。主権(la sovranita)は、或るひとつの関係が存在するとき、その関係を構成する人々を個別に取り上げた場合のだれそれに属しているのではなく、その関係自体に属しているのである」。上村忠男編訳『クローチェ政治哲学論集』、法政大学出版局、1986年、16-17頁。卓見である。主権論には、プラトン以来、次の類型がある。単独支配(専制政治・君主政治)・少数支配(寡頭政治・貴族政治)・多数支配(民主主義・衆愚政治)。これらはいずれも政治に関わる人数で区分している。それに対してクローチェは、実体か関係かで区別する。参考:中村勝己「クローチェの自由主義とゴベッティ以降の反ファシズム――クローチェの『政治学綱要』(1924年)をめぐって」(『大学院研究年報』第33 号、法学研究科篇、2004年2月発行、中央大学、510 頁)。大類やその弟子にあたる酒井三郎は、クローチェを高く評価している。私は、その酒井の弟子であり、したがって、大類の孫弟子にあたる。以下の写真は、1932年に東北帝国大学西洋史研究会が創刊した『西洋史研究』の表紙である。中村、大類、酒井らが紙面を飾っている。
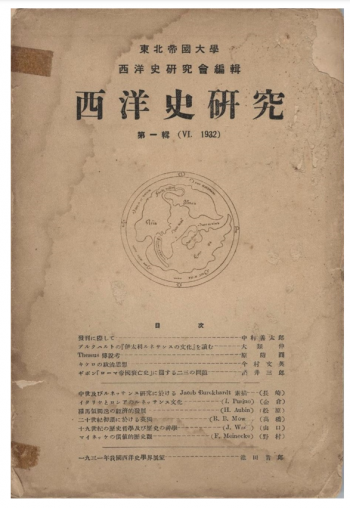
(いしづかまさひで)
(pubspace-x,2025.09.20)
